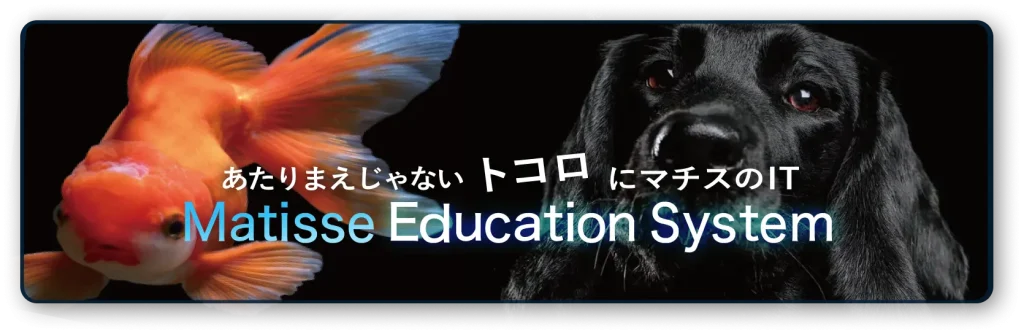創業から教育事業に尽力してきたマチス
スクールや通信教育の事業から始まり、ネットワーク優勢の新しい時代に答えるシステムの基盤を強化してきました。技術者の提供・教育・システムの強化やカスタマイズ開発…と、求められる技術を高め、IT技術の目覚ましい進歩に食らいつき、成長した結果はそのまま自社開発技術の向上にもつながりました。
私たちが大切にしていること
教育の冠の元、デジタル人材不足の課題解決を
労働人口の減少は、深刻な社会問題です。
AI技術も注目される中、デジタル人材をどう増やしていくのか。教育事業では教育における社会課題を解決するべく、プログラマーの育成に力を入れています。
豊富な経験を持つ講師や、Eラーニング、最新の技術を取り入れた独自のカリキュラムによる実践力を考慮した人材の育成を目指しています。
学びを共有することで生まれる社会性の構築と、情報共有の強化で個々の成長を促し、スキルに合わせた実戦経験を持つことで、理解を深める。
どの成長段階でも活躍できる場を提供するサイクルこそが、人とテクノロジーの可能性を引き出し、持続可能な社会の実現に貢献すると考えています。
このように「次世代を育てる」社会貢献性に賛同するメンバーが集まることで、自社だけでなくIT事業における社会的価値を高めていけると考えております。

自社開発技術、その新事業
近年では特にエネルギーに関する分野で自社システムの開発、運用に力を入れています。他社とのコミュニティを築きながら、精力的に新しい事業の創出にチャレンジしながら、結果としてSDGsの達成にも貢献するなど、サスティナビリティに目を向けた動きにも注目しています。
持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

私たちの仕事
人工増加に伴うタンパク質クライシスに打ち勝つ
2050年に97億人を突破すると予想される人口増加に伴う、タンパク質の供給不足の問題への対策として様々な企業が、豆を使った自社開発や、昆虫を使った研究を進めています。
マチスでは、食の問題の対策として、大規模な陸上養殖システムの開発を行なっています。テクノロジーによる最も効率的な食材の育成と供給で、食の問題を直接解決する未来。フィリピンなど、海外のノウハウを取り入れ、システム管理をするために、砂漠化した立地にも命を吹き込むことも可能です。
更に稼働地域に新たな雇用を産み、廃棄食材の活用など、多角的な視点で社会問題を解決しています。
こうして、ご協力いただける企業様や沖縄の琉球大学の研究なども巻き込みながら循環するサイクルの構築のヒントとして、ノウハウの提供も積極的に行なっております。
農産物の生産者が減少を続ける高齢化問題と食育
農家を営む経営者の平均年齢が80歳を超えることをご存知でしょうか。
減少を続ける国産農作物と、大企業による大量生産によって、多くの食卓が農薬や添加物の含まれた食品で埋まっています。
そんな中、50年以上続く「食といのちと守る会」を運営する、青木紀代美さんがずっと訴え続けている、「本当に安心安全な食材」を選ぶ大切さと、その食材を作る「農家を守っていかねばならない」という思想に賛同し、食育の情報配信と安全な食材の販売を行う、ECサイトを運営しております。
このように、食の問題を解決しながら、流通先となるWeb化システムも自社で一貫して運用できる強みが、同じように知識を必要とするS Iの事業でも喜ばれています。
あたりまえじゃないトコロにマチスのIT
まだIT化してないトコロにシステムと可能性を!
近年のWeb化が急加速した時代でも、昔ながらの伝統を守り、
人が持つ五感や熟年の勘に頼った技術を生業としている起業様は少なくありません。
マチスは、このようにまだITに触れていない事業やコンテンツに着目し、積極的に参入することで、古くからの知識や、味、技術のような、失ってはいけない、かけがえのない物を守っています。
例えば人間の五感、触感、音、匂いといった、職人の感性に頼った分野にまで分析、機械化、システム化を導入することで、働き方を助け、効率や、品質の精度を高める事ができます。関わる起業様のこぼしたお困りごとの中には、まだ見ぬ多くのシステムが生まれるヒントが隠されています。
既存のシステムを組み合わせてパズルのように問題解決に繋げていくシステム開発の現場には、柔軟性とクリエイティブな発想力、新しい技術や社会のニーズへの敏感さが求められます。
だからこそ、常に新しい発見とシステムが生まれ続けるIT事業には、安定した需要と面白さあるのではないでしょうか。